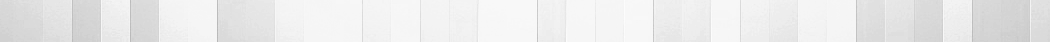ソーシャル・ビジネスや社会的起業と言われる世界では、
これまで企業が当然のように追い求めてきた「利益」が敵視される
ような傾向があります。
この利益敵視については、2つのレベルがあります。
1. 企業が当期利益を出すことそのものを問題視する
2. 企業が当期利益を株主に配当することを問題視する
(当期利益を利益剰余金とし、再投資することは問題視しない)
1の立場をとる方は、そもそも感情的に「企業」「ビジネス」というものが嫌いな方々です。
「非営利」という言葉を大切にする人々はこの立場をとります。
しかし、最近、ソーシャル・ビジネスという言葉が普及するにつれ、
1の考えの方々は相対的に少なくなってきているような印象を受けます。
多くの人が、利益そのものが悪いのではなく、
「利益の最大化」ではない「健全な利益」が重要なのだと主張しています。
特に、低所得者層に融資を行うグラミン銀行(マイクロファイナンス)を設立した
功績で、ノーベル平和賞を受賞したムハンマド・ユヌス氏が、
ソーシャル・ビジネスの定義の一つとして、
「投資家は投資額のみを回収できる。投資の元本を超える配当は行われない」
を挙げ、上記の2の利益敵視の考え方が流行ってきています。
しかし、僕は、2つの理由から、このユヌスの考え方にも疑問を持っています。
1. なぜ配当ばかりを責めるのか?
会計の知識がある方ならご存知かと思いますが、
企業の利害関係者が受け取る「報酬」の中で、配当はそのひとつにすぎません。
主な利害関係者の受け取る報酬としては、以下のものが挙げられます。
・株主への報酬=配当金
・債権者への報酬=利子
・経営者・従業員への報酬=給与
利子や給与は費用として扱われるため、当期利益を算出する際には、
すでに差し引かれています。
例えば、アメリカの投資銀行の経営陣が莫大な報酬を受け取ることが、
メディアで取り沙汰されますが、
彼らが受け取っている給与は、当期利益には含まれません。
どれだけ「利益追求」行動の結果、売上を増やしたとしても、
給与報酬を上げれば、費用の額が大きくなり、利益にはなりません。
ユヌス氏の考え方に基づくと、ソーシャル・ビジネスにおいては、
債権者や経営陣、従業員は報酬が得られるのに、株主だけが報酬を
受け取れないという、非常に不公正な状況を生んでしまいます。
2. 株主もコストを負っている
ファイナンスの世界で、株主への配当金や債権者に対する利子の支払いを
「資本コスト」と呼びます。
これは、ものや情報を購入したり、従業員を雇ったりした場合にコストが発生
するように、調達したお金にもコストが発生するという考え方からです。
企業はコストを負って資金を調達し、それを投資して売上を得ています。
そして、その投資リターンと資本コストの差額が利益になるわけです。
(議論の単純化のため、その他のコストは無視しています)
この原則から考えると、ユヌス氏の発想は、株主を大きく苦しめます。
ソーシャル・ビジネスへの株主となる企業は、
資本コストを負って資金調達をしているにも関わらず、
投資からのリターンを得られず、その投資は純損失を生んでしまうからです。
グラミン銀行そのものは、低所得者層への融資からリターンを得ており、
資本コストという考え方を理解しているはずです。。
債権者の立場で投下した資本からリターンが得られるのであれば、
同様に株主に対してもリターンを認めるべきだと思います。
一方で、ユヌス氏のグラミン銀行は、多くの大企業からの投資を集めることができて
いるのも、また事実です。
しかし、中小企業が同じことをすることは2つの理由からかなりハードルが高いのです。
1つ目は流動資産の問題です。
大企業は手元に流動資産が多く、
ソーシャル・ビジネスへの投資に要した資本(株式発行や借入れ)への資本コストを、
その投資リターン以外から支払うことができます。
しかし、資金に余裕のない中小企業は、投資リターンが得られないと、資本コストの
支払いができなくなってしまい、資金繰りが回らなくなってしまいまうのです。
2つ目は投資目的の違いです。
大企業はソーシャル・ビジネスへの投資を一種のCSR活動、広義のブランディング、
マーケティング活動として位置付けることができます。
ソーシャル・ビジネスへの投資は、メディアなどが「無料で」宣伝してくれます。
さらに、企業イメージや製品イメージが向上し、販売促進にもつながります。
そのためCSR投資を一種のマーケティング予算として捉えることができます。
他方、中小企業は規模が小さいため、ソーシャル・ビジネスへの投資を、
本業として扱わざるをえません。
すなわち、本業としてこの投資から利益を得ないと、
会社の財務状況を悪化させてしまいます。
ユヌス氏は社会発展のために小さな企業をサポートする活動を行う一方で、
他の中小企業を市場から排除してしまう構図を生んでしまっています。
このように冒頭で紹介した、
「企業が当期利益を株主に配当することを問題視する」という考え方については、
アメリカでも賛否両論があります。
反対意見からは、
通常の(=利益分配型の)高評価の社会サービス企業が、
ソーシャル・ビジネスという分類から排除されてしまい、
彼らのモチベーションを下げてしまう、という意見も出ています。
ユヌス氏が、社会への(=事業への)再投資を願ったうえで上記のように定義を
した考え方には理解をします。
また、利益を上げにくいソーシャル・ビジネスの世界で、利益志向ではなく、
ミッション志向でないと、事業の継続が難しいということも理解できます。
一方で、利益は新たな事業を創造するための原資であり、
利益を「健全な利益」と「悪徳な利益」に分類することも容易ではありません。
ミッション志向で事業を行った結果、生じた利益を配当したとしても、
その企業はソーシャル・ビジネス(社会企業)と呼んでいいと考えます。